月刊・教室だより
名物先生によるリレー連載(毎月20日更新)
【連載第218回】
ステレオセットが我が家に来たころ
長野のいなかの家の客間にステレオセットがうやうやしく鎮座したのは、多分私が小学校4年生の頃でした。私たち兄弟は、音楽を聴くのはテレビかラジオでたまたま流れたものを聴くのみで、何か好きなものを選んでかけるなんて発想はそれまではありませんでしたから、とても興奮したのを覚えています。父親が、ステレオ導入に合わせて何枚かLPを買ってきて、初めてLPをプレーヤーにかけるのを見ました。
そのLPのラインアップは今思うとなかなか優れたものでした。
父が特に好きと言っていた、ショパンのノクターンの入った名曲集はルビンシュタインの演奏、また、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲は何か思い出でもあるかのように「この(転調した)メロディがきれいなんだ」と呟いていたのを覚えています。メニューインの独奏、フルトヴェングラーの指揮(ルツェルン祝祭管弦楽団)でした。シューベルトの「未完成」交響曲もフルトヴェングラー指揮、ウィーンフィル。シューベルトの「ロザムンデ」序曲、ヨハン・シュトラウスⅡの、「皇帝円舞曲」も入っていて、今でもロザムンデを聴くとなんとも言えない懐かしい気分になります。
フリッツ・ライナー指揮のシカゴ交響楽団でベートーヴェンの交響曲第6番「田園」。メンデルスゾーンとチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲はハイフェッツの独奏、サラサーテの「ツィゴイネル・ワイゼン」もカップリングされていて、よく聴きました。兄弟そろってチャイコフスキーの第一楽章をかけて、オーケストラが主題を高らかに総奏するところを「ジャン・ジャーン」聞こうよ、と楽しんでいたのを覚えています。今でも私にとって最高のヴァイオリニストはヤッシャ・ハイフェッツです。
クワイ河マーチなどの入ったミッチ・ミラー合唱団の名曲集、レーモン・ルフェーブル楽団のイージーリスニング曲集なんかもありました。
妹が聴きたいといって買ってきてもらったベートーヴェンの交響曲第5番「運命」は、ケンペ指揮、チューリッヒトーンハレ管弦楽団。私がせがんで初めて買ってきてもらったのがビゼーの「アルルの女」組曲、カラヤン指揮のベルリンフィルの最高の演奏でした。小学校の音楽の時間の音楽鑑賞で聴かせてもらったビゼーの「アルルの女」第二組曲の最後の「ファランドール」、2つの主題が合体するところがおもしろいなあ、というのが、私のクラシック音楽との出会いだったのです。それで私はクラシックにハマりました。
そのあと、初めて自分で買ったのがやはり学校で聞いて「山の魔王の宮殿にて」にワクワクしたグリーグの「ペールギュント」組曲、やはりカラヤン、ベルリンフィルでした。3枚目までははっきり覚えています。ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」、フルトヴェングラー指揮の、バイロイト祝祭管弦楽団による演奏でした。あの頃は私にとってLP1枚1枚が大事件で、ドキドキしながらレコードに針を落としていたものでした。
平日は会社勤め、遠い会社だったので朝6:00台に家を出て、19:20頃帰宅、土日は家の田んぼと畑の世話で忙しくしていた父親が、ゆっくりステレオに向かって音楽を聞いている姿は、全く記憶にありません。そんなことも、なんだかしんみり思い出す夏です。
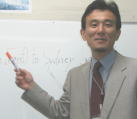 高橋先生 高橋先生 |